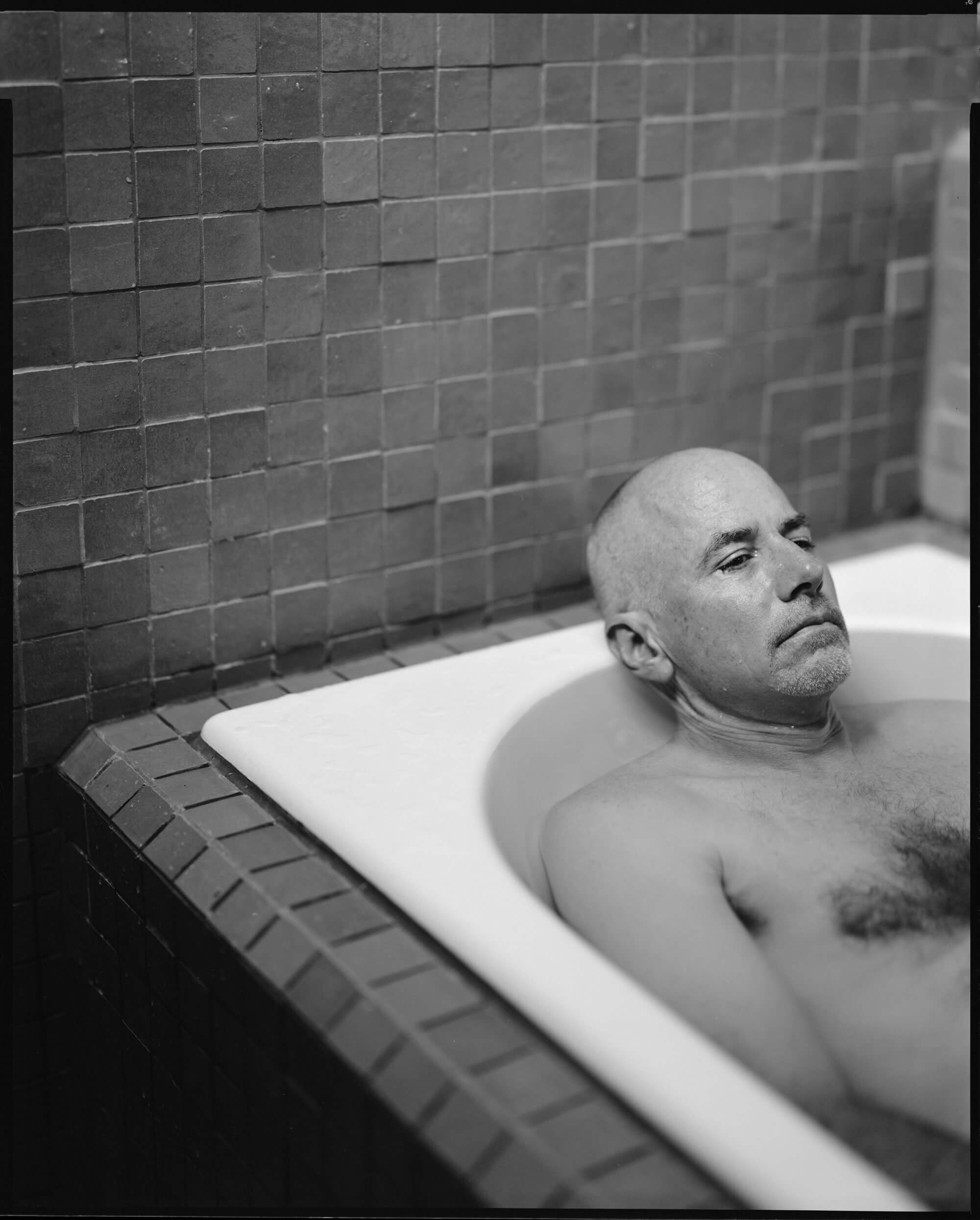
ピーター・アイビー #アーティスト
―テキサス州オースティンでお生まれだそうですが、どういうところですか?
私がオースティンに住んでいたのは70年・80年代で、ちょうどヒッピー時代が終わる頃ですね。今はだいぶ変わっていると思うけど、とても自由な環境で住みやすかったです。子供たちは夜になると走り回って、街中や橋の下、川沿いで遊んで過ごすようなところで。もちろん危ないこともありましたけど、そこまで心配する必要はなくて、とにかく自由だったんです。裸足で、上半身裸で駆け回ってたりして。高校時代は大きなボトルのビールとステーキを買って、自転車で公園に行ったりして、のんきに遊んでました。ほんとうにのんびりしてたんですね。
―ピーターさんはどういう子供でしたか?
どうでしょうか (笑)。子供の頃はとにかく…ただただ外に出たかったから。親から離れたかったので、行き先が決まっていなくてもとにかく外に出て自転車を乗り回っていましたね。どこかに行く…どこかにたどり着くというよりは、どこかに向かうということが目的で。
例えば、自転車で湖まで行って、その湖がある公園の一部には崖もあって。夜真っ暗で何も見えない中、崖から飛び降りてはまた登って、また飛び降りて…10メートルくらいの高さはあったと思うけど、そんな風に遊んでたね。それから冒険が好きでした。あの時は今と違って、やることがそんなになかったから。自分が知ってること、自分の知識に頼る必要がありました。今みたいに何でもすぐ調べたりすることはできなかったですからね。当時の方が色々とゆったりしてた気がします。とにかく子供の時は外で遊んでいたかったんです。あとは水辺か水中にいたかったですね、暑かったので。そうして、いろんなところを歩き回ってたから、方向感覚がすごく磨かれました。一切迷わない。どこに行っても問題なく家に戻れるんです。それが初めて訪れる場所だったとしてもね。
―そういった幼少期の経験の蓄積が、自分の根っこを育てていったと思いますか?
もちろん。今自分に対してある自信は全て、幼少期にやっていたこと、あの時代にあの場所で過ごした経験から来てると思います。若い頃からだいぶ自立してたので。あと、オースティンは音楽文化が有名な街で、ライブはしょっちゅう行ってました。それが普通でしたね。なので、クリエティブな面ではそれもとても大きな影響でした。とても楽しかったですよ。特に当時はちょっと反抗的な雰囲気があってパンクロックがオースティンではすごく人気があったんです。私はその時代のパンクロックにすごく影響を受けてました。社会に批判的な意見を持つことがはやってたんです。私たち自身は世の中的には流行に乗ってたとは言えないですけどね。当時そういう音楽を聞いてる人はむしろアウトサイダーと見られてたので。そういう意味では、今でもアウトサイダーとして見られたとしても居心地が悪いと感じたことはないです。そういうのは今まで気にしたことがないので。
―ご家族はピーターさんのプロダクトについて、美しさの感覚は共有されていますか?
私の両親-母親、父親と継父ですね、母は再婚したので。母親と父親は2人ともミュージシャンでした。そのため美学や繊細さや表現力などに対しての意識はとても高かったです。でも「もの」になると、その意識は少し薄れたみたいですね。彼ら的には例えば、「水を入れられるのであれば」と、そのものが機能的であればそれでいい、という感じでものを見ていました。なので、少しは理解しているけど完全ではないです。(私の作品を)好きでいてくれるし、価値を認めてくれています。でも、例えば、透明の作品よりは色がある作品の方が好みなんじゃないかな。欧米の多くの人たちがそうだと思いますよ、日本に比べると。その違いが多少はありますね。
―アメリカにおいてガラス職人は職人、アーティストのどのような見方をしている人が多いと感じますか?
それは…なかなか複雑ですね。
「ガラスアーティスト」として名乗る人たちが多いと思います。例えばちょっとした色がついていたりするシンプルなタンブラーをつくる人でさえ「アーティスト」になりうる。なので、「ガラスアーティスト」はかなり広い範囲の人たちを含むフレーズです。今自分が日本でやっていることをアメリカでやっていたとしたら、おそらく仕事にならなかったと思います。アメリカではシンプルな透明の手作りグラスタンブラーを「ガラスアート」としてカテゴライズするのは難しいからです。その違いを自ら実感した時、ここ(日本)には自分の居場所があると感じました。
なかなか答えにくいですが、「これは芸術なのか、工芸なのか」というガラスや陶芸などにまつわる古典的な議論があって。美術学校に行っていたら必ず議題になるので皆さんも聞いたことがあるかもしれませんね。でも芸術と工芸の違いって、ある意味華やかさの違いでしかない気もします。あとは値段でしょうか。欧米ではずっと議論されてきていて。今はもう落ち着いたかもしれませんが、私が学生の時代もずっと「これは果たしてアートなのか」とみんなぶつぶつ言い合ってました。なので、「アート」を作ってる人にはよく「君のガラスはアートじゃない、ただの工芸だ」と言われてたんですけど、それって誰が決めるの?っていつも思っていました。ものづくりをしている人たちの間では絶えない議題でしたね。70年代ごろから始まった事でしょうか。私にとっては本当にとるにたらない、一切興味が持てない議題でした。「そんなのどうだっていいじゃん、何だっていいじゃん」って思ってましたね。誰かが話題にすると必ずさけていました。自分の作品の話をする時、結構何にでも当てはまるんですけど、カテゴリーは便利である一方でとても制限的でもあります。そして、とあるものがとあるカテゴリーとして分けられてしまうと、そのトピック自体もかなり枠組みされてしまうんです。自ら物事を見たり考える前に、既に「これはこうなんだ」って言われているような…例えば、子供に「アイス欲しい?」って聞いたら、もちろん「欲しい」って答えますよね。でも、「何が欲しい?」と聞くと、水だったりミルクだったり。なので、こういうカテゴリーを使うと物事がとても推定的になってしまうんですね。便利な時もありますが、時にはすごく邪魔な要素だと思います。
―ピーターさんが、そういったことを議論する機会は日本ではありましたか?
ありませんね(笑)。愛地教育大学で教えてる時期がありましたが。その頃は、そういう話を学生としてました。でも普段は話さないですね。たまに一緒に仕事してる人とはするかもしれないけど、個人的な意見ぐらいです。ジョン・バージャーの『イメージ―視覚とメディア』は、こういった議論に関してよく書かれているので読む価値がありますよ。
―ここ富山では多くのガラス作家がたくさんいると思いますが、作家同志で議論を行いたいと思ったことはありますか?
自分のバックグラウンドは…ガラスという手段でアートを作っていました。専門学校との違いは、私たちは芸術の哲学を学んでいたんです。他の人たちとアートに関して話さない理由もこれで、あくまでも哲学なんですね。日本では「職人」に対してとてもオープンで敬意ももっています。さっきの話に戻ると、日本ではアーティストは職人を尊敬し、職人はアーティストを尊敬していると思います。でもアメリカの場合いはこの二つは競争している。そういうところで大きな違いがありますね。ヨーロッパではそうでもないと思いますが、アメリカでは「職人」は美術的な視点からするとちょっと無学なイメージがあるというか…彼らはただものをつくることが好きで、彼ら自身何で好きか知らないし分からないし、なんのためにやってるか分からない、というイメージです。私にとってはそのイメージはとても視野が狭いと思いますけどね。でも実際にそういうイメージがありました。日本で「職人」というのはそのものについて勉強し把握していて、そういう意味では学があるという風に見られますよね。
―高校卒業後、大学に行かずに車の整備士や大工の見習いをしていたそうですね。直接大学に行かなかったのはなぜですか?
高校生の頃は何にも興味を示さず、やりたいことがない自分に対して両親は不安を感じていました。高校時代はただただ自転車に乗り回っているガキという風にしか見られてなかったので。この子は一体どうやって社会で生き延びていくんだ、と感じてたと思います。特に継父はとてもしっかりしていて努力家だったので。とにかくすごくて、いまでもガンガン働いています。そういう意味で彼からはとても良い影響を受けました。彼からしたら私は風来坊のようなものだったので、理解もできなかったでしょうし、かなり心配されました。なので、高校を卒業したらリベラルアーツを学びに行けと勧められたんです。リベラルアーツ(学芸)は簡単にいうと高校の続きのようなものです。彼ら的には、そこから専門を決めればいい、と思ったのでしょう。でも私はその時点で現実社会を経験したかった。あと、どう使えば良いか分からない知識をこれ以上学ぶことにはうんざりでした。もし学びたいことが見つかったらその時に学べばいい、それまで普通に働こうと自分で勝手に決めて、働き始めました。その結果、とてもいい経験になったんです。自分も聞かれましたが、大人はよく自分の子供に「何になりたいの?何がしたいの?」と聞きます。でも、「何をしたくないのか」を知って気づいていくことも同じくらい大切なんだと思います。自分の子供には学校に行くことを勧めますが、しばらく働いても良いんじゃないかとも思います。自分が進みたいかもはっきりしない道を全力で進み始める前に、まずは世の中がどういうところかを経験した方が良いんじゃないかと思います。
―働いている中でアートを勉強したいと思うようになったんですね。
高校生の時にはアートには全然興味がありませんでした。アートの意味もわからなかった。ですが「文化」「フィロソフィー」「考え」にはすごく興味がありました。
私がガラスをはじめたのは偶然で。働いて学んだことは体で覚える仕事が好きということでしたね。ですが単純作業の繰り返しはやりたくないとはっきり感じていました。それと1人よりチームで動くのが好きということも。友達がRISDーRhode Island School of Designに通っていたので、その友人から大学のことを教えてもらって大学に興味が湧いてきたんです。
―その大学の特色とは、どういったものですか?
子供時代によく瞑想やESP(超心理学)についての本を読んでましたが、そういった哲学的な興味をくすぐる要素が、当時その大学にあると感じたんです。例えばダダイズムのような自分でもまだ触れ始めたばかりのものが学べる環境でした。そして、その大学に一番ひかれた理由は、私が興味を持っているアイディアを元にいろんなものが作られてたことです。その大学に通っていた友達から学校で何をやっているかを聞いていくうちに、いろんな思考をものづくりを通して探るプロセスにすごく興味を持ちました。それは自分の中で今までにない発想でした。世界共通語に関してのディスカッションなど、とにかく何もかも魅力的でした。当時の美大ではそのようなトピックはよく話されていたことだと思いますが。特にRISDは学生にとってはとても圧のかかる環境でしたね。求められる作業量はすごくて、当時国内で一番大変と言われてた大学がMITとRISDでした。そのプレッシャーは個人的にはチャレンジと捉えられたので、私にとっては良い環境でしたが。
さっき話したように、オースティンに住んでいた頃はパンクロックにハマっていて、独創的な思考や意見が多かったんです。でも、そこには「パーティしようぜ!」みたいな雰囲気もあって、思いっきりふざけて暴れまくっても、「俺たちオルタナティブだからいいんだ!」って言ってればいいような。だけど、RISDのことを知った時、若い頃から身についてきた独創的な思考や哲学を、ちゃんとプロフェッショナルに文学的に問い続ける方法を見つけ出せたんです。
―学生たちの熱量が高そうな大学だったんですね。
熱量はとても高かったですね。正直つらいこともありました。自分の全てをつぎ込んで作品を作ったとしても、その作品が良くないと言われることが多かったですね。それでしかない、未完成だ、これじゃ全然ダメだ、と言われるのはかなりきついですが、他の人が言われるのを見るのもつらかったです。そんなせいか、学生たちにはdo or die(やるか死ぬか / 死ぬ覚悟でやる)という、もしかしたら無駄に過激な意識があったんです。もしアーティストとして成功するのであれば、これを乗り越えないといけない。乗り越えられないものはアーティストになれない、そこで全ては終わり。なので、自分にプレッシャーをかけすぎたり、頑張りすぎてボロボロになっていく学生はよくいました。楽しそうだから美大に行こうと思ったら、現実は全然違ったり。正直、かなり過酷な環境ではありました。そういう意味では、大学に行く前に働いていた経験はとても役に立ちましたね。ガラスを最初に学び始めた頃、必死に頑張りました。ほとんど寝ずにとにかく腕を磨くために作業し続けたりして。ガラスのクラスは小さかったので1人の先生が全体のコースを仕切っていて。で、真っ当ではあったけど、彼は私に常にF(落第)かC(最低限達成)の成績しか出してくれないんです。そんな成績ばかりだったので、「どうしろというんだ?彼は何を求めてるんだ?一体ここで何を学べというのか?」とずっと疑問に思ってました。でも、そのうち「あんなやつどうだっていい」と探るのをやめて、自分がしたいことをし始めたんです。すると、まるで魔法かのように全てがうまくいきました。そしたら彼は「ようやく分かったのか、自分が何をやりたいのか」、と。学校側から何かを与えられるのを待つのではなく、こっちから欲しいものをどんどん学校から取っていくことにしたんです。「あと2年しかないし学費も高いし、成績なんてどうでもいいから自分が求めてるもの全部取ってやろう」ってね。そこからは無敵でした。やりたい放題で最高でしたね。
―日本の大学と考え方が違いますね。
アメリカは大体勉強のために行きます。日本は勉強以外の人間関係のことを大事にしている人が多いですよね。アメリカはその部分は無視しています。日本は人間関係を無視しないで大学生活を過ごしていますね。遊びが中心な気がします。なので社会人になると真面目にしないといけないと思って怖がる子が多いです。日本とアメリカの間をとればいいんじゃないかなと思いますけどね。
―ガラスを専攻した理由はなんだったんですか?
ロードアイランドはアメリカで最初に産業工場が建てられた場所です。ものすごく大きな産業地域で、ニューヨークが有名になる前は、工場の持ち主が住むロードアイランド・ニューポートが最も裕福な街として知られてました。そこではいろんなものが製造されていて、様々な工場も揃っていたんです。その産業をデザインする人たちも必要だったので、私が知る限りRhode Island School of Designは技術や製造プロセスを学んだり、様々な機械に触れて自由にスキルを磨ける場所をそのデザイナーたちに与えていました。課題などを通してその技術を教えていたんですね。デザイナーになるためにはまずその機械を通して基本を学ぶ必要があったんです。私がガラスを選んだ理由…ちょっと長い話になってしまいますが。私もまずデザインから始まりました。この学校はまずデザインの基礎を学ぶところから始まります。当時もそれは学校の原理でしたね。私が当時作りたかったのは、「美術的に表現力のあるもの」と「機能性のあるもの」の間の「なにか」でした。使い勝手が良く、かつ何かを表現しているようなもの。今もそれを続けていますね。CADを使ったデザインも教え始めてましたが、私はパソコンに全く興味が持てなかったんです。人と一緒だったり、直接ものに触れて作業をするのが好きでした。デザインをするためにパソコン技術を学ぶことは本当に興味がなかった。とある一学期、専門で進みたいコースがなくて、自分の専門外クラスを一学期だけ取ることは可能だったので、ガラスの授業を受けることにしました。たまたまガラスを選んだだけで。その前に何回かガラス工房に行ったことがあって、1年目のプロジェクトのために部品を作ったことはあったのですが、その時に面白いなと思って。そんな流れで、ガラスを発見したというか、学び始めたんです。すごい興味深くて、何かを繋げたり、自分が作ったものを固定したりできることがね。
―ピーターさんがガラスに向き合う中で沸点があがったところってどこでしたか?
自分でも意外でしたけど、純粋に技術を学ぶことにどハマりしました。どうやったら上手く形を作れるか。こんなに何かに夢中になるのは初めてだったので、自分でも驚きでした。常にチャレンジだったのが、手が上達していくと、同時に目も上達していくんですね。前よりも何かを上手く作れるようになるけど、目はそれを追い超していて、問題をみつけたり「いや、まだまだ、もっと上手くできる」という風に見てるんです。技術が上達すればするほど、目も常に上達してその先を見ています。今でもそうですが、常に挑戦です。馬の目の前にぶら下がるにんじんのような感じですね。馬はそのにんじんを目掛けて動き続けるけど、にんじんが常に前にいる。当時のガラス専門学生たちが本当にいい人たちばかりで。私の先輩たち、彼らは今でも世界的にトップクラスのガラス職人です。何かを学ぶには本当に創造力に富む環境でしたね。私はその刺激に反応して、その場を離れたくないと思うほど、とにかく豊かな環境でした。
―RISD(Rhode Island School of Design)以外でガラスを勉強する機会はあったんですか?
ちょうど卒業した頃、シアトルから来たとても有名な作家の手伝いを6週間ほどしました。シアトルは技術に優れた人たちが集まるコミュニティーがあるんです。彼とも友人になりましたし卒業した先輩もシアトルに行っていたので私も卒業後はシアトルに行きました。そこで、いろんな工房に働きに行きました。いつも仕事がちゃんと入ってきたので幅広く学べて、技術的には良い機会でした。それから、ベネチアへも行きました。古い技法を扱っている工房があると聞いたので、2週間、毎日その工場へ通って勉強しました。それが初めてのヨーロッパだったけど工場しか行かずに帰りました。
―ベネチアの職人の方は技術を気軽に教えてくれたんですか?
あの時代でも、全く教えてくれないような頑固な人は稀でしたね。昔だったら職人が逃げたら殺す、というくらい技術は守られてきました。技術の担い手が、すごく少なくなった時期から、少しずつ増えてきて今は完全にオープンになっています。
―ピーターさんの作品はシンプルに見えますが技法は複雑なのでしょうか?
技術を見学しにスウェーデンやドイツにも行ったことがあります。それぞれの場所でやり方の違いはありました。でも、どう言えばいいのかな…技法は大きく2つあって、10通りある訳じゃないです。細かい部分の違いはさまざまありますが、歴史的に効率的な手法を見ると、そこまで違いはないです。この人たちは木製の道具を使って、こっちの人たちは鉄製の道具を使ってる、など、そういった違いはあるかもしれませんが道具の使い方は基本的に同じです。私はいわゆる修行のようなものは通ってこなかったんです。欧米の大学で学び、そのあといろんな人の下で働いていろんなものを見てきました。ある人からはこれを取って、あの人からはあれを取って、と。ガラスを始めてから日本に来るまで、たくさんのいろんなことを体験できたことはとてもラッキーに思ってます。その経験から様々な手法を組み合わせてきました。なので、イタリアの技術も取り込んでいます。私のガラスの作り方の一部は、イタリアのおじいちゃんたちしか使わない手法だったりします。でも彼らももう長くは活動できないので、そうするとその手法を普段使ってるのは私だけになるかもしれません。その手法は繊細で薄いガラスをつくるためのもので、小さなガラス工芸でしか使えず、大きなものには適していません。だから、他の国、例えば大きくて色んな形を作りがちのアメリカなどではこの手法はそんなに使われていませんね。私は手法を、例えばスウェーデン式だったり、よくいろんな手法を組み合わせてます。そこから自分の独特なやり方を作り上げてきました。どんな職人でも、素材を知ることが必要だと思います。誰かと同じ方法が決して自分にあってるとは言えないですから。例えば誰かのやり方を見て、自分もこうやってみたいと思うことはあると思います。そのやり方を真似ることはできますが、そこには自分の感覚ややり方が必ず含まれますね。
―ピーターさんは自分の作品・工房・技術の継承、全てを大事になさっていますね。
作品はそこまで大切だとは思ってません。でも、つくるものに対して、そのデザインやデザインを作り上げる技術に関してはプライドを持ってます。その作品を欲しいと言ってくれる人、使ってくれる人がいる限り、作品には存在し続けて欲しいと思います。それ以外、いわゆる「作品」以外、「自宅」や「工房」も私の作品です。自分が作り上げた環境の中で人々がガラスを使ってること自体、私の作品です。ある意味ちょっと別ラインのプロジェクトと言ってもいいでしょうか。このプロジェクトに対してつぎ込んでるので、続いてくれるといいなと願ってます。ここに来る人たちはここに来たくています。学びたい、学び続けたい人たちが。そしてこれからもこのようなことを学びたい人は出てくると思います。ただ、学べる環境は少なくなってきていると思いますね。ここで成し遂げたいことは、伝統的な工房での弟子入りシステムに現代経済を組み込んだものです。ある意味、新しいモデルだと思います。いわゆる見習いや弟子として学びながら、作家としての見習いというか。私の希望は、自分が作り上げる作品を継続すること以外に、この場所で人々がこの技術を通してものづくりを続けられること。手法的な面でも哲学的な面でも、ここで身につけるスキルがその人のためになり、その人がやり遂げたいことのためになることです。
―ピーターさんからどんなことを学びたいと思ってきているんでしょうかね?
それは直接、みんなに聞いたほうが良いですね(笑)。
以下、お弟子さん。
(お弟子さん)私は2年間、富山のガラスの専門学校で勉強してました。ピーターが、一番最初の工房をつくっているときに出会ったんです。ペンキ塗のアルバイトを探していると聞いて友達と行きました。作業しながら会話している中で、「卒業したらどうしますか?」「いやちょっと、ガラスを勉強しに海外へ行こうかなって思ってまーす。」「なんで海外行くの?」「日本でもできるんじゃない?」みたいな話になって。日本にいてアメリカ人のピーターが工房を作ろうとしてる。じゃあここがベストなのでは!と思ったんです。技術が絶対的にあるっていうのは分かっていました。まず、「もの」。人を動かす力があるというか、揺さぶられるような力がある。それが何かを勉強したいって思いました。ガラスの技術だけじゃなくて、ピーターっていう人や文化にも興味がありました。この人から何かを学びたいって思ったんです。
―海外からも多くのかたが訪れるんですか?
彼らがここにくる理由は、作品のデザイン性とこの素材とプロセスでしか作り上げられない何かを感じとっているからです。言いたいこととしては、ここで作っている作品は決して簡単に作れるものではありません。デザインもよく考えられたものだと思いたいです。ここに来たい人たちは1人で訪れることが多いですが、それは職人としてデザインのことを学びたいからだと思います。
―ガラスを扱っているときのマイルールはありますか?
自分の作品でストイックに決めてるのが、つくるプロセスの印のような、跡のようなものを残すことです。何百年間も、ガラス職人の目的は何も跡を残さないということでした。まるで水のような素材から魔法のように形にしていくみたいにね。人間の手で作られたものではないように見せることだったんです。それはルネッサンス時代に教え込まれたことで、今でも残ってる慣習です。ガラス作家として、お店でガラスを見るときに、まず真っ先にするのが作品の裏面を見ることです。陶芸家も同じようなことをしますね。裏面を見ることによって、どのようにその作品が作られたかのディテールを探すんです。個人的には説明を必要としないものが好きですね、見ればヒントがあるようなものが。全て把握することはできないかもしれないけれども、何かしら情報を得ることはできるかもしれない。何年もずっと見続けても理解できないことや、ものはあまり興味がありません。啓蒙時代のおもちゃにはすごく影響を受けてますね、あの時代のおもちゃは説明を必要としないので。結構根深いです。
―日本でガラス作家として生きていくことは難しいですか?
私は自分の経験でしか話せないので、他の人がどうかは言えませんが。でも、私が先生だった頃、卒業後に自分の作品を作り続ける方法が見出せない学生が多かったです。何人かは続けられましたが、ほとんどは…仕事としてやりがいのない事をされたり、自分たちの作品との繋がりが見つけ出せなかったり。つくる側として、ガラス業界はとても厳しいと思います。まず、設備がすごく高い。経済的に恵まれてる人でも、まず基本的なスタジオをつくるために大体600万とか800万くらいかかります。スタジオがあれば作品は作れますが、実際その作品を売るのはまた全然別の話になってきます。その上燃費、手伝ってくれるアシスタントも雇わなければいけない。経済的な支援があったとしても、かなり厳しいと思います。よくあるのが、学び続けたいものをビジネスとして開業するけど、そのビジネスを保ち続けるために「学ぶ」ことを諦めないといけなくなること。
―ピーターさんの作品が世の中に受け入れられたことを、どう思っていますか?
とてもラッキーで、とても恵まれています。多くの人に支えられていることもありがたいと思っています。私が作ってきたもの、それに対しての思想、私の行動を信じてくれているギャラリーがあります。彼らは私とお客さんとを繋げてくれたので、本当に感謝しています。そしてお客さんたちに「これ持っています」とか、「これ使ってます、すごい気に入ってます」とか言ってもらえるのは、本当にありがたい限りです。
こうなったきっかけが…『TAIKI』という、とても出来の良いクラフトに関しての雑誌でした。なぜか私の作品をどこかで見て、私をインタビューしたい、と連絡があって。当時私が住んでいる瀬戸まできてくれました。そしてそのインタビューが載った号を1部送ってくれたんですが、すごく良い紙で写真もどれも美しく、くだらない広告も全くない。とにかく上品な雑誌でした。1冊2,000円ほどしたので、決して安くはないですね。その雑誌を見た南青山にあるギャラリーワッツのオーナー川崎さんとパートナーの詩野さんから瀬戸にいるあなたに会いたいと連絡があったんです。残念ながら川崎さんはもう亡くなられてしまいました。その時私は瀬戸の古い工場に住んでいて、その2人が「東京であなたを代表したい、展示しに来てください」と。私にオファーするほど作品に興味を持って信じてくれたので、その機会をくれた彼ら(『TAIKI』・ギャラリーワッツ)には今でも本当に感謝しています。
―ピーターさんはご自身のフィロソフィーをみる人に理解させる気がありますか?
私の願いとしては、どう言えば良いか…例えば、2個のグラス、一見すると同じもののように見えますけど。でも並べて見ると、違いますね。最初は、「ああ、美しい」という感じで、違いが全く見えません。でも時間が経つにつれ、一つは少し斜めになっているとか、そういう所に気づき始めます。それぞれ違う名前がある風に見えてきます。棚に並んでる作品はいっぺん同じに見えますが、私からしたらどれがどれかが一瞬で見分けられます。ものと過ごす時間が長くなればなるほど、その作品を知ることができると思うんです。結構な時間がかかるとは思いますが。あなたに誰も知らない一面があるように、私にも誰も知らない一面もあり、本人にしか分からないこともあります。なので作品を完全に知ることができるのはその作品を作った人のみだと思います。他のガラス職人が私の作品を見たら、技術的にどう作ったのかわかるかもしれませんが、私が何を感じていたのかは伝わらないかもしれません。
―きれい、美しいと思う心を育むために大切なことは何だと思いますか?
時間が大事だと思います。自分がつくった作品は、それ一つを見ているわけではなく今まで作った作品全部と見比べているんです。そういった視点から自分の作品を見ています。作り上げたその時「もの」との距離は近い。ですが時間が経過すると、どんどんその作品たちが遠下がって、ある程度の距離を置いた状態で見えるようになっていきます。過去には何かをつくる時、ある一つのことに熱心になったり、すごく難しいことを挑戦していました。ですがやり遂げると自分がいつの間にか違うものに興味を持っていたり好んでいたことに気づくんです。
例えば、このガラス。形が良い、面白い、遊び心がある、技術的に難しいことをしてる、他のガラス職人が見てもとてもいい出来だと言ってくれるかもしれません。でも同じ時に、ただ水がのみたいときに、このグラスではなく、こっちのグラスを手にとるかもしれません。そうなると、「なんでこれが好きなんだろう?実際使うのはこっちなのに。その好きになる要素はなんだろう?」って考え始めるんですね。それは無意識のプロセスなんです。なので個人的な意見ですが…そうですね、自分の作品を知るためにも、分かるためにも時間が掛かります。日本で教師をやっていた頃、大学では学生にアイディアを作り上げ、それを形にすることを要求していました。それが私には本当に理解できなかったんです。つくる前にその作品を理解することなんてできるでしょうか(笑)?それは私が学生時代にもあったことですが、日本で教えてる時もそうでした。私の場合、つくること自体が考えるプロセスなので。
―ガラスづくりを辞めようと思ったことはありますか?
ガラスを続けるかは分かりませんが…ガラスは一つのポテンシャル、ものづくりの一つの方法でしかないのですが、形はともあれ、ものづくりは続けます。
中森さんと私の作品の違いは、中森さんの目は私の手よりも長続きします。そのうち作りたくても肉体的に作れなくなる時期が来るかもしれません。でも、それで悲しんだりすることはないと思います。何か違うことをすればいいだけなので。建築にも興味があるし、植物も好きです。他にもやったら面白そうと思うことはたくさんあります。
ピーター アイビー Peter Ivy
1969年、アメリカ・アラバマ州生まれ。自らの名を冠したガラス器ブランドの創設者であり、デザインから制作まで自ら手掛けるアーティスト兼職人、また、クリエイティブ・ディレクター。
芸術的かつ極めて機能的な器を制作する。テキサス州オースティンで育ち、若いうちから車のリストアや大工の経験を経た後に、美術に関心を持つようになる。
その後Rhode Island School of Designにて美術学士号を取得し、母校及びMassachusetts College of Artで教員を務める。
2002年に来日し、以後5年間、愛知教育大学ガラス学科の教員として知識や経験を伝えることで後進の育成に努める。
この経験を機に彼はフォルムとシンプルさをより重要視するようになり、それが現在も作品づくりの基礎となった。ガラス制作への意欲が高まるにつれ、2007年に富山の農村部に転居。古民家の納屋に手作りの工房を作る。ガラス器に対する彼のミニマリスト的なアプローチは当時売られていた西洋風の装飾的なガラス器とは対照的で、ガラス工芸の新潮流の先がけとして国内外で広く評価を得た。












